1. はじめに ― なぜ「暴落対応型ポートフォリオ」が必要
2025年10月、日本株市場はおよそ30年ぶりの本格的な上昇相場を維持しながらも、表面下では複数の外部リスクが同時進行している。
- 米大統領選を控えた政策の不確実性(トランプ再浮上と再関税発言)
- 米中関税再燃による世界貿易秩序の再緊張化
- 日本国内の政局不透明化(公明党の連立離脱・石破ショックなど)
これらは現時点で金融危機を伴うものではないが、市場のセンチメントが悪化すれば、短期的な20〜30%級の調整(=中規模暴落)が発生するリスクは否定できない。
しかし、そのような「恐怖の局面」こそ、長期投資家にとって最良の買い場である。
本レポートでは、「暴落が来たら買いたい銘柄」を、流行や人気ではなく、構造的な強さ・財務の安定性・歴史的な株価データをもとに選び出した。
その目的は、暴落のたびに市場から逃げるのではなく、“暴落を待って買う”戦略を定量的に組み立てることにある。
2. 選定プロセス ― 定量と定性を統合した三段階アプローチ
【STEP 1】歴史的ボトムの実測
リーマンショック(2008年)、チャイナショック(2015年)、コロナショック(2020年)といった過去の主要暴落期における
PER・PBRの最安値レンジを定量的に収集。
その水準を「企業が本質的に過小評価された水準」として、現在の実勢と比較。
【STEP 2】企業価値の持続性の検証
暴落時にも企業価値が毀損しにくい構造を持つ企業を選定。
具体的には以下の条件を満たすこと。
- 世界・国内で圧倒的な市場シェア・技術的優位性を有する
- 財務が強固(自己資本比率60%以上または実質無借金)
- キャッシュフローが安定し、長期にわたって自社株買い・配当を継続可能
【STEP 3】“暴落耐性 × 再評価ポテンシャル”スコアの付与
- 暴落しても赤字転落や資金繰り悪化が起きない(耐性)
- 景気正常化局面でEPS・ROEが戻りやすい(再評価)
この二軸を基準にスコアリングを行い、最終的に上位6銘柄を選出した。
3. 選定結果 ― 「暴落が来たら買いたい」6銘柄一覧(2025年10月10日時点)
| 銘柄 | 証券コード | 10/10終値 | 歴史的ボトム水準(目安) | 狙い株価 | 想定下落率 | 割安判断の根拠 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京エレクトロン | 8035 | 29,280円 | PER13倍/PBR2.3倍 | 19,000円前後 | ▲35% | 世界装置3強。財務比率70%超。過去ショック期のレンジ目安(再現を保証しない)。 |
| 信越化学工業 | 4063 | 5,020円 | PER10倍/PBR1倍 | 3,500円前後 | ▲30% | 半導体用シリコンウエハで世界首位級。キャッシュ潤沢。リーマン・コロナ期の反発水準。 |
| トヨタ自動車 | 7203 | 2,898円 | PER8倍/PBR0.8倍 | 2,000円前後 | ▲31% | 世界販売首位。PBR1倍割れが長期マネー流入点。円高局面でも耐性強。 |
| キーエンス | 6861 | 60,440円 | PER20倍/PBR2.8倍 | 39,000円前後 | ▲36% | 高収益・無借金。営業利益率50%超。主要ショック期にPER20倍前後まで低下の例。 |
| 任天堂 | 7974 | 12,385円 | PER10倍/PBR1.3倍 | 8,600円前後 | ▲31% | キャッシュリッチ。新ハード移行期にPERが低位化する傾向(10倍前後の局面例)。IP資産強力。 |
| 伊藤忠商事 | 8001 | 8,539円 | PER7倍/PBR0.8倍 | 6,400円前後 | ▲25% | 商社バリュー指標。PBR1倍割れ・利回り3%台が買いシグナル。 |
注:本表の「歴史的ボトム水準(目安)」は、2008/2015/2020など主要下落局面の実績レンジを参照し、当時の実績EPS・純資産を基準に算出した“目安値”です。個別企業・業種ごとの収益構造によりばらつきがあり、将来の再現を保証するものではありません。
4. ファクトチェック:暴落の現実的シナリオ
- 「石破ショック」は2024年9月末に発生した政局急変に伴う一時的急落で、
30%級の暴落ではない。
これは金融危機型ではなく、「政局ショック」型。 - 30%級の下落が実際に発生したのは、
リーマンショック(2008〜09)やコロナショック(2020)といった
信用収縮・流動性危機を伴う局面のみ。
よって本レポートの“30%級暴落シナリオ”は、
「石破ショック」のような政局トリガーを起点に、金利上昇・為替急変・海外リスクが重なった複合パニックを想定している。
5. 分析の背景 ― 歴史的データに基づく「本気買い」水準
過去のリーマン・チャイナ・コロナ各ショックを通じて観察された共通点は明確である。
- PER10〜13倍、PBR1倍前後は“恐怖時の割安圏”として観測される傾向があるが、業種・企業特性によってばらつきが大きい。特に超高収益・高品質プレミアムが恒常的に評価される企業では、このレンジに到達しない場合もある。
- 現在(2025年10月)時点の主要銘柄は、その水準よりおおむね20〜40%高い位置にある。
このことは、今後市場が急落した際に、
「歴史的割安圏」=長期資金が再び流入する水準が、
おおよそ現在株価から30〜35%下のゾーンにあることを意味する。
よって、
「石破ショック級の政局不安」や「金融リスク再燃」で市場が20〜30%下落する局面が到来した場合、
それは“企業価値の崩壊”ではなく、“長期投資家が再参入するための合理的価格帯”になる。
この水準に達したとき、恐怖ではなく“冷静な買い”ができるかどうかが、長期投資家の真価を分けることになる。
6. 結論 ― 暴落は恐怖ではなく、構造的なチャンス
この6銘柄は、いずれも日本を代表する「グローバル競争力 × 財務健全性 × 高利益率」の三拍子がそろった企業群である。
彼らの株価は短期的な調整で揺れても、企業価値そのものはほとんど毀損しない。
暴落が来たときこそ、
“恐怖のど真ん中で拾えるか”が勝敗を決める。
これらの価格帯は「暴落でしか届かない真のバリューライン」であり、
市場が恐怖に包まれたその瞬間こそ、“最も合理的な買い場”である。
本稿の見解は2025年10月12日現在に基づき、記載の価格・指標は2025年10月10日終値を基準としています。
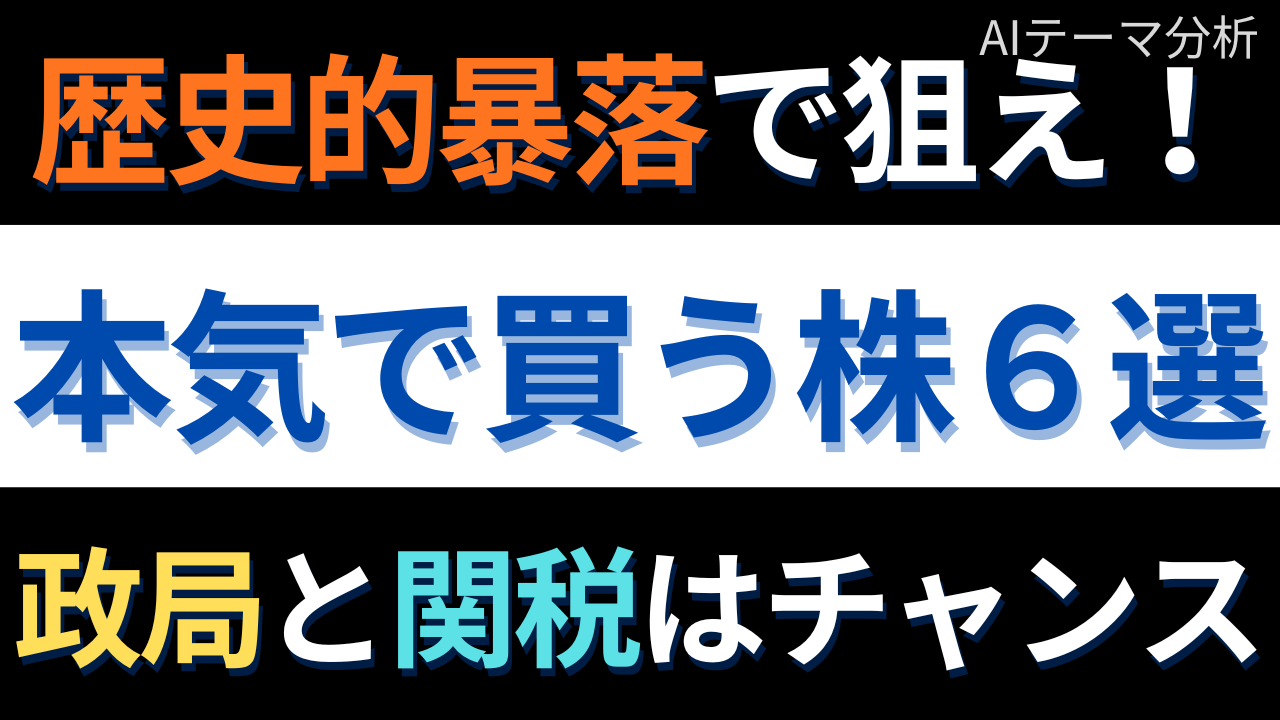
-8-120x68.png)
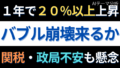
コメント