パルグループホールディングスの株価は、直近の最高値2,948円(2025年9月10日)から、2025年10月17日終値の1,951円に至るまで、約33%という大幅な調整局面を迎えています。この下落は、同社が2026年2月期第2四半期で増収増益を達成し、衣料・雑貨事業ともに好調を維持しているにもかかわらず発生しています。
1. 現状認識:最高値からの大幅調整と市場の疑問
現在の株価1,951円は、2026年2月期の会社予想に基づく1株当たり当期純利益(EPS)97.03円(株式分割後基準)に対して、PER(株価収益率)20.1倍で評価されています。最高値圏では、これよりも高い成長期待が織り込まれていたため、現在の株価調整は、市場環境の変化に伴うバリュエーション(評価倍率)の修正圧力と、需給の悪化という構造的な要因によって引き起こされていると分析されます。
■スナップショット(2026/2期 会社予想・直近株価ベース)
- 株価:1,951円(2025/10/17 終値)
- EPS(予想):97.03円(分割後基準)
- PER:約20.1倍(株価÷EPS)
- PBR:約4.53倍
- BPS(逆算):約431円(株価÷PBR)
2. 業績の好調持続と成長の牽引役
2026年2月期の中間連結会計期間(2025年3月1日~8月31日)の業績は、売上高1,170億82百万円(前年同期比15.6%増)、営業利益140億95百万円(同19.4%増)、親会社株主に帰属する中間純利益91億86百万円(同19.8%増)と、売上高、利益ともに大幅な増収増益を達成しました。
衣料事業の戦略的成功
衣料事業の売上高は705億81百万円と大きく増加。SNSアカウントを通じた社員インフルエンサーが強固な繋がりを構築し、先行予約を中心に正価販売の比率を高めることに成功。需要に応じて発注数量を調整し、売れ残り在庫の圧縮を通じて売上総利益率の向上に寄与しています。
雑貨事業(3COINS)の高成長
雑貨事業の売上高は462億79百万円で大幅な増収増益。大型店舗の新規出店の継続と300円超の新商品の積極投入により客単価上昇と売上総利益率の改善を実現。海外再挑戦として7月に香港、8月にマレーシアに地域1号店をオープン。
■セグメントの概況(中間期)
- 衣料:売上高 705億81百万円/SNS×先行予約で正価販売比率向上・在庫圧縮→粗利率改善
- 雑貨(3COINS):売上高 462億79百万円/大型店出店継続・300円超ライン強化→客単価上昇・粗利率改善/海外1号店
3. 下落の構造的要因:マクロの逆風とコスト圧力
国内消費の不透明感
賃上げは進む一方、食品価格や人件費の上昇で物価が高止まりし、実質賃金はマイナス、個人消費は力強さを欠く状況。景気刺激策も見込みづらく、小売業の成長性に対する警戒感が継続。
コスト高と先行投資負担
人件費や地代の上昇によるコスト高の圧力は利益率の重荷。雑貨事業の海外出店や国内大型店展開といった積極投資フェーズは将来の成長の土台だが、短期的にはコスト先行となり評価倍率の切り下げ圧力に。
需給の悪化
信用倍率は11.57倍と買い長。高値圏で積み上がった信用買いが戻り売りとなり、回復の重荷に。
4. 定量分析による理論的な底値圏の特定
2026年2月期のEPS 97.03円を基礎に、保守的なPER水準とPBR水準からフロア感を試算。
PERレンジに基づく底値試算
・ベア(PER 16倍):97.03円×16=約1,550円
・ディープベア(PER 14倍):97.03円×14=約1,360円
PBRレンジに基づくフロア感
・前提:株価1,951円、PBR 4.53倍 → BPS 逆算 約431円
・PBR 3.5倍:431円×3.5=約1,510円
⇒ 総合所見:PBR 3.5倍(約1,510円)とPER 16倍(約1,550円)が重なり、1,510~1,550円前後が段階的な買い入れ検討ゾーン。
5. 底打ち・反転を見極めるための五つの定量的モノサシ
- 在庫管理の効率性:在庫の伸び率 ≦ 売上の伸び率 が持続
- 雑貨(3COINS)の収益性:四半期粗利率が前年比 +0.5pt以上の改善
- 衣料の販売効率:既存店売上が四半期ベースで前年比 +2%超の持続
- 信用需給:信用倍率が現在の11.57倍→5倍以下へ低下
- 海外1号店のKPI:坪効率・粗利率が国内と遜色ない水準の確認
6. まとめと投資戦略
株価調整は、マクロの不透明感と需給の悪化による高い成長期待の修正が主因。理論的な底値ゾーンはPERとPBR分析から1,510円~1,550円前後。このゾーンでの初回買い入れ検討に加え、上記5指標のうち2~3項目が同時に改善する四半期データを待って、本格的なトレンド追随を図る戦略が有効。

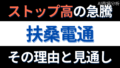
-14-120x68.png)
コメント