2025年10月5日、総務省によるドローンおよび「空飛ぶクルマ」(eVTOL)の遠隔操縦に関する電波法規制緩和の方針が報じられた。この規制緩和は、単なる技術利用の許可ではなく、地上通信網と衛星や高高度プラットフォーム(HAPS)などの非地上ネットワーク(NTN)を統合し、日本の通信インフラを三次元的に拡張する国家戦略の転換点と位置づけられる。この政策転換は、これまで通信の信頼性がボトルネックとなっていた山間部や海上でのドローン物流、インフラ点検、災害対応、そして将来の都市航空交通(UAM)の実現に向けた技術的基盤を整備するものであり、株式市場に対し、次世代インフラの構築とそれに伴う新市場の創出という長期的な構造変化を見据えた戦略的アセットアロケーションを求めている。
規制という触媒 ― 空域の解放と安全基準
今回の規制緩和は、日本の空を新たな経済活動の場として開放するための、総務省と国土交通省(MLIT)という二つの強力な省庁にまたがる複雑かつ意図的な国家インフラ構築の第一歩である。
総務省の規制緩和を解剖する
総務省の方針は、ドローンや空飛ぶクルマの遠隔操縦に衛星通信やHAPSを利用可能にするという点で画期的である。この動きは、情報通信審議会が主導する「高高度プラットフォーム(HAPS)の技術的条件」の策定作業と連動している。
この制度整備の技術的な本質は、特定の周波数帯の割り当てと利用条件の明確化にある。現行制度で上空利用が可能なのは主にFDD方式の800MHz、900MHz、1.7GHz、2GHz帯であり、2.5GHz帯(TDD)は検討段階にある。HAPSと地上ゲートウェイ局を結ぶフィーダ/バックホールについては、38GHz帯等での実証が進展しており、具体的な割当レンジは制度化過程で確定していく。これらの周波数は、既存の携帯電話網の帯域と重複・隣接するため、干渉を回避しつつ共存するための詳細な技術的条件が定められる。この規制緩和は、「現状は衛星通信が使えるのは地上/高度3000m超に限られる」といった暫定的な高度制限を取り払い、地上から成層圏までシームレスな通信環境を構築するという明確な政策意図の表れである。
通信法と航空法の交差点:レベル4飛行の実現
投資家や事業者が認識すべき最も重要な点は、この新しい市場が総務省と国土交通省の連携によってのみ成立する点である。国土交通省が定める無人航空機の飛行レベル、特に「レベル4」(有人地帯における補助者なし目視外飛行)の実現が、高付加価値サービスの鍵となる。
航空法に基づくレベル4飛行の許可・承認を得るためには、「通信途絶」リスクへの厳格な対策が求められる。HAPSや衛星通信によって提供される、地上インフラに依存しない常時接続・低遅延の通信リンクは、レベル4飛行における通信途絶リスクを劇的に低減させる。すなわち、総務省が許可する新しい通信手段は、国土交通省がレベル4飛行を承認するための技術的な前提条件そのものとなる。
さらに、将来的にドローンやeVTOLが高密度で飛行する空域を管理するための「無人航空機運航管理システム(UTM)」の導入が官民で検討されており、今回整備されるNTN通信インフラが、UTMの神経網として機能することになる。
新たな通信パラダイム ― HAPS、衛星、そして3Dネットワーク
規制緩和がもたらすのは、地上、成層圏、宇宙空間の各層を連携させた「3Dネットワーク」という、通信の質そのものを変革する新たなパラダイムである。
HAPS:成層圏のアドバンテージ
高高度プラットフォーム(HAPS)は、地上約20kmの成層圏を無着陸で飛行する無人航空機に通信基地局を搭載したものであり、「空飛ぶ基地局」とも呼ばれる。HAPSは、従来の地上基地局と通信衛星の間に存在する「ミッシングリンク」を埋める存在として重要である。
HAPSの利点は、地上基地局と比較して1機で直径100kmから200kmという広大なエリアをカバーできる点、および高度36,000kmの静止軌道(GEO)衛星と比較して地上との距離が圧倒的に近いため、通信の遅延が大幅に少なく、低遅延性を両立できる点にある。リアルタイムでの機体制御が求められるドローンや空飛ぶクルマの遠隔操縦において、この低遅延性は生命線となる。
多層統合ネットワークの構築
HAPS、低軌道(LEO)衛星、静止軌道(GEO)衛星、そして地上の5G/6Gネットワークは、互いに補完的な関係にある。この多層的なネットワークを統合し、利用者がインフラの違いを意識することなく最適な通信を享受できる世界を目指すのがNTNの最終的なビジョンである。
NTTグループの「宇宙統合コンピューティング・ネットワーク」構想は、この統合を推進しており、各層の役割は以下のように明確化されている。
- 地上5G/6Gネットワーク: 人口密集地の都市部における超高速・大容量通信。
- HAPS(成層圏): 地方都市、山間部、海上などを広域にカバーし、ドローンや空飛ぶクルマ向けの低遅延通信を担う。
- LEO衛星(低軌道): 地球全体をカバーし、これまで通信が届かなかった地域に高速ブロードバンド接続を提供する。
この多層統合ネットワークの構築は、地上インフラの制約から解放された、真にレジリエントで信頼性の高い通信能力を国家レベルで確保することを意味し、ドローン物流や自動運転といった次世代の自律制御社会を支える基盤そのものとなる。
空の覇権争い ― キャリア戦略と株価への影響
規制緩和を追い風に、国内大手通信キャリア3社は、それぞれ異なる技術とパートナーシップを選択し、次世代の覇権争いに突入した。この戦略的分岐は、各社の将来の収益構造と企業価値を大きく左右する。
HAPSの旗手たち:NTTとソフトバンク
NTT(9432)とソフトバンク(9434)は、HAPSをNTN戦略の中核に据え、産業用自律制御市場の覇権を狙う。
- NTTグループ(NTTドコモ / Space Compass):
- 戦略:スカパーJSATとの合弁会社Space Compassを核とし、IOWN構想の一環としてHAPSを位置づける。
- 技術:エアバス傘下のAALTO社「Zephyr」を使用し、ケニア上空で地上のスマートフォンへ直接LTEデータ通信を行う世界初の実証に成功。
- 目標:2026年度中の国内商用サービス開始を目指す。基礎研究から社会実装までを見据えた重厚長大なモデルである。
- 株価への影響:高い技術的・実行リスクを伴うが、成功すれば産業の根幹を握るプラットフォーマーとなる大きなリターンが期待できる。長期的な国家インフラ構築テーマとして注視される。
- ソフトバンク:
- 戦略:市場への早期投入と先行者利益を狙うアグレッシブなスケジュールを持つ。
- 技術:米国のSceye社に出資し、飛行船のようなLTA型HAPSの導入を検討。
- 目標:2026年に日本国内でプレ商用サービスを開始、2027年以降に本格的な商用サービスへの移行を公表している。俊敏な事業開発主導型モデルである。
- 株価への影響:NTTと同様に高いリスクを伴うが、アグレッシブなタイムラインは、技術実証やサービス開始のニュースフローが出やすく、短期的な株価変動のカタリストとなりやすい。
LEOの挑戦者:KDDIのStarlink同盟
KDDI(9433)は、自社開発を行わず、SpaceX社のLEO衛星コンステレーション「Starlink」との戦略的提携を選択した。これは、資本効率と市場投入スピードを最大化する「プラットフォーム統合」モデルである。
- 戦略:グローバルで最も先進的なパートナーと組み、広域カバレッジと市場投入の速さを武器とする。
- サービス:第一段階として、光ファイバー敷設が困難な地域のau基地局のバックホール回線にStarlinkを活用。第二段階として、特別なアンテナを必要としない「Direct to Cell」サービスを2025年4月に開始し、まずはSMSから、将来的には音声通話やデータ通信への対応も計画している。
- 株価への影響:自社の開発負担は軽く、より早期に収益化を実現できる可能性がある。パートナー依存リスクはあるものの、Starlinkとの提携進展や「圏外」解消によるコンシューマー向けサービスへの貢献が、株価を左右する。
拡大するエコシステム ― バリューチェーン全体の投資機会
NTN革命の影響は、通信キャリアに留まらず、広範な産業に波及する。NTNの実現を支える「縁の下の力持ち」企業群にこそ、分散された、しかし確実な投資機会が存在する。
コアインフラと通信機器(中期)
- 日本電気(NEC, 6701)と富士通(6702)は、HAPSに搭載される通信ペイロード、地上とHAPSを結ぶゲートウェイ局、NTN環境に対応した基地局ソフトウェアの開発・製造において中心的な役割を担う。 Beyond 5G/6Gを見据えた国家プロジェクトと連動しており、中期的な収益貢献が期待される。
専門技術と計測(短期)
- アンリツ(6754)は、NTN通信特有の課題(ドップラー効果、長大な伝搬遅延)を正確に再現し、通信チップセットや端末の性能を検証するための計測ソリューションを提供する。同社の製品はNTN対応機器の開発に必須のツールであり、NTN市場が拡大すればするほど、その需要は確実に増加する。アンリツは、どのキャリアの戦略が成功するかに関わらず、市場全体の成長から恩恵を受ける**「トールロード(料金所)」的なビジネスモデル**を持つため、短期間での業績インパクトが期待される。
- スカパーJSATホールディングス(9412)は、NTTとの合弁会社Space Compassを通じてHAPS事業の当事者となっており、長年の衛星運用ノウハウに加え、HAPSという新たな成長ドライバーを得る。短期的な収益インパクトが見込まれる。
アプリケーションとドローン産業(短期)
- ACSL(6232)は、国産ドローンのリーディングカンパニーであり、NTNによる信頼性の高い通信リンクの確立は、同社のビジネスモデルを根本から変える。NTNによって全国の山間部や離島でも安全なレベル4飛行が可能になれば、過疎地への物流や広大なインフラ点検といったユースケースが、実証から本格的な商業サービスへと移行する。キャリアグレードのNTN接続性は、ACSLのソリューションの信頼性を飛躍的に高め、官公庁や大手インフラ企業からの受注拡大に直結する直接的受益者となる。
先端素材と部品(長期)
HAPSの長期滞空を可能にするための高性能な素材と電子部品を供給する企業群は、長期的な構造的成長ポテンシャルを持つ。
- 先端素材: HAPS機体の極めて高い軽量性・高剛性・耐久性を満たすため、炭素繊維複合材料(CFRP)が不可欠となる。東レ(3402)と帝人(3401)は世界的なリーダーであり、HAPSの量産化が進めば安定した需要が見込まれる。
- パワー半導体: 太陽光を唯一の動力源とするHAPSのエネルギーマネジメントには、高効率な電力変換・制御を行うパワー半導体が不可欠である。特に電力損失が少ない炭化ケイ素(SiC)や窒化ガリウム(GaN)を用いた次世代材料が重要となる。ローム(6963)や富士電機(6504)は、この分野で高い技術力を持ち、高付加価値な製品を提供する機会を得る。
これらの「イネーブラー」企業への投資は、特定のキャリアの成功に賭けるリスクを分散させ、NTNというメガトレンド全体に分散投資する効果がある。
結論:投資テーマと戦略的提言
日本の空で始まろうとしている通信革命は、短期的なテーマ物色ではなく、次世代の産業革命を支える基盤そのものを構築する試みである。
投資家は、以下のドライバーとリスク要因を注視し、投資ホライズンに合わせたポートフォリオを構築することが重要となる。
注目すべきドライバー
- 技術的マイルストーン:HAPSの3ヶ月以上の連続飛行成功、NTN通信を用いたレベル4飛行の国内初成功など。
- 規制・政策の進展:国土交通省によるUTMサービスプロバイダ認定制度の正式な導入、およびNTNを前提とした運航ルールの策定。
- 大型契約の獲得:大手電力・ガス会社や防衛省、警察庁などからのNTNサービスやドローンソリューションの大型受注。
注意すべきリスク要因
- 技術的失敗:HAPSの試験機墜落や、開発コストが想定を大幅に上回る商用化計画の遅延。
- 規制の停滞:省庁間の制度調整の難航によるレベル4飛行の承認プロセスの停滞。
- 社会的受容性:ドローンやeVTOLの事故、騒音問題などによる社会的な逆風。
このNTNメガトレンドへの投資は、時間軸とリスク許容度に応じて、以下のように階層的にアプローチすることが有効である。
- Tier 1(直接的受益者): NTT、ソフトバンク、KDDI
- 市場創出から最も直接的な恩恵を受けるが、巨額の投資と戦略実行に関するリスクも最も大きい。
- Tier 2(中核的イネーブラー): スカパーJSAT、アンリツ
- 特定のキャリアの戦略に依存せず、NTN市場全体の成長から恩恵を受ける。特にアンリツは、開発初期段階での需要増加が見込まれる。
- Tier 3(長期エコシステム): ACSL、NEC、富士通、東レ、ローム、富士電機
- 市場が本格的に立ち上がるまでには時間を要するが、アプリケーション側での直接的受益者(ACSL)や、構造的な成長ポテンシャルを持つ素材・部品の供給者として、長期的な視点での投資機会を提供する。
三次元通信革命:総務省の規制緩和が解き放つドローン・空飛ぶクルマ市場と関連銘柄の行方
2025年10月5日、日本経済新聞は、総務省によるドローンおよび「空飛ぶクルマ」(eVTOL)の遠隔操縦に関する電波法規制緩和の方針を報じた。この規制緩和は、単なる技術利用の許可ではなく、地上通信網と衛星や高高度プラットフォーム(HAPS)などの非地上ネットワーク(NTN)を統合し、日本の通信インフラを三次元的に拡張する国家戦略の転換点と位置づけられる。この政策転換は、これまで通信の信頼性がボトルネックとなっていた山間部や海上でのドローン物流、インフラ点検、災害対応、そして将来の都市航空交通(UAM)の実現に向けた技術的基盤を整備するものであり、株式市場に対し、次世代インフラの構築とそれに伴う新市場の創出という長期的な構造変化を見据えた戦略的アセットアロケーションを求めている。
規制という触媒 ― 空域の解放と安全基準
今回の規制緩和は、日本の空を新たな経済活動の場として開放するための、総務省と国土交通省(MLIT)という二つの強力な省庁にまたがる複雑かつ意図的な国家インフラ構築の第一歩である。
総務省の規制緩和を解剖する
総務省の方針は、ドローンや空飛ぶクルマの遠隔操縦に衛星通信やHAPSを利用可能にするという点で画期的である。この動きは、情報通信審議会が主導する「高高度プラットフォーム(HAPS)の技術的条件」の策定作業と連動している。
この制度整備の技術的な本質は、特定の周波数帯の割り当てと利用条件の明確化にある。現行制度で上空利用が可能なのは主にFDD方式の800MHz、900MHz、1.7GHz、2GHz帯であり、2.5GHz帯(TDD)は検討段階にある。HAPSと地上ゲートウェイ局を結ぶフィーダ/バックホールについては、38GHz帯等での実証が進展しており、具体的な割当レンジは制度化過程で確定していく。これらの周波数は、既存の携帯電話網の帯域と重複・隣接するため、干渉を回避しつつ共存するための詳細な技術的条件が定められる。この規制緩和は、「現状は衛星通信が使えるのは地上/高度3000m超に限られる」といった暫定的な高度制限を取り払い、地上から成層圏までシームレスな通信環境を構築するという明確な政策意図の表れである。
通信法と航空法の交差点:レベル4飛行の実現
投資家や事業者が認識すべき最も重要な点は、この新しい市場が総務省と国土交通省の連携によってのみ成立する点である。国土交通省が定める無人航空機の飛行レベル、特に「レベル4」(有人地帯における補助者なし目視外飛行)の実現が、高付加価値サービスの鍵となる。
航空法に基づくレベル4飛行の許可・承認を得るためには、「通信途絶」リスクへの厳格な対策が求められる。HAPSや衛星通信によって提供される、地上インフラに依存しない常時接続・低遅延の通信リンクは、レベル4飛行における通信途絶リスクを劇的に低減させる。すなわち、総務省が許可する新しい通信手段は、国土交通省がレベル4飛行を承認するための技術的な前提条件そのものとなる。
さらに、将来的にドローンやeVTOLが高密度で飛行する空域を管理するための「無人航空機運航管理システム(UTM)」の導入が官民で検討されており、今回整備されるNTN通信インフラが、UTMの神経網として機能することになる。
新たな通信パラダイム ― HAPS、衛星、そして3Dネットワーク
規制緩和がもたらすのは、地上、成層圏、宇宙空間の各層を連携させた「3Dネットワーク」という、通信の質そのものを変革する新たなパラダイムである。
HAPS:成層圏のアドバンテージ
高高度プラットフォーム(HAPS)は、地上約20kmの成層圏を無着陸で飛行する無人航空機に通信基地局を搭載したものであり、「空飛ぶ基地局」とも呼ばれる。HAPSは、従来の地上基地局と通信衛星の間に存在する「ミッシングリンク」を埋める存在として重要である。
HAPSの利点は、地上基地局と比較して1機で直径100kmから200kmという広大なエリアをカバーできる点、および高度36,000kmの静止軌道(GEO)衛星と比較して地上との距離が圧倒的に近いため、通信の遅延が大幅に少なく、低遅延性を両立できる点にある。リアルタイムでの機体制御が求められるドローンや空飛ぶクルマの遠隔操縦において、この低遅延性は生命線となる。
多層統合ネットワークの構築
HAPS、低軌道(LEO)衛星、静止軌道(GEO)衛星、そして地上の5G/6Gネットワークは、互いに補完的な関係にある。この多層的なネットワークを統合し、利用者がインフラの違いを意識することなく最適な通信を享受できる世界を目指すのがNTNの最終的なビジョンである。
NTTグループの「宇宙統合コンピューティング・ネットワーク」構想は、この統合を推進しており、各層の役割は以下のように明確化されている。
- 地上5G/6Gネットワーク: 人口密集地の都市部における超高速・大容量通信。
- HAPS(成層圏): 地方都市、山間部、海上などを広域にカバーし、ドローンや空飛ぶクルマ向けの低遅延通信を担う。
- LEO衛星(低軌道): 地球全体をカバーし、これまで通信が届かなかった地域に高速ブロードバンド接続を提供する。
この多層統合ネットワークの構築は、地上インフラの制約から解放された、真にレジリエントで信頼性の高い通信能力を国家レベルで確保することを意味し、ドローン物流や自動運転といった次世代の自律制御社会を支える基盤そのものとなる。
空の覇権争い ― キャリア戦略と株価への影響
規制緩和を追い風に、国内大手通信キャリア3社は、それぞれ異なる技術とパートナーシップを選択し、次世代の覇権争いに突入した。この戦略的分岐は、各社の将来の収益構造と企業価値を大きく左右する。
HAPSの旗手たち:NTTとソフトバンク
NTT(9432)とソフトバンク(9434)は、HAPSをNTN戦略の中核に据え、産業用自律制御市場の覇権を狙う。
- NTTグループ(NTTドコモ / Space Compass):
- 戦略:スカパーJSATとの合弁会社Space Compassを核とし、IOWN構想の一環としてHAPSを位置づける。
- 技術:エアバス傘下のAALTO社「Zephyr」を使用し、ケニア上空で地上のスマートフォンへ直接LTEデータ通信を行う世界初の実証に成功。
- 目標:2026年度中の国内商用サービス開始を目指す。基礎研究から社会実装までを見据えた重厚長大なモデルである。
- 株価への影響:高い技術的・実行リスクを伴うが、成功すれば産業の根幹を握るプラットフォーマーとなる大きなリターンが期待できる。長期的な国家インフラ構築テーマとして注視される。
- ソフトバンク:
- 戦略:市場への早期投入と先行者利益を狙うアグレッシブなスケジュールを持つ。
- 技術:米国のSceye社に出資し、飛行船のようなLTA型HAPSの導入を検討。
- 目標:2026年に日本国内でプレ商用サービスを開始、2027年以降に本格的な商用サービスへの移行を公表している。俊敏な事業開発主導型モデルである。
- 株価への影響:NTTと同様に高いリスクを伴うが、アグレッシブなタイムラインは、技術実証やサービス開始のニュースフローが出やすく、短期的な株価変動のカタリストとなりやすい。
LEOの挑戦者:KDDIのStarlink同盟
KDDI(9433)は、自社開発を行わず、SpaceX社のLEO衛星コンステレーション「Starlink」との戦略的提携を選択した。これは、資本効率と市場投入スピードを最大化する「プラットフォーム統合」モデルである。
- 戦略:グローバルで最も先進的なパートナーと組み、広域カバレッジと市場投入の速さを武器とする。
- サービス:第一段階として、光ファイバー敷設が困難な地域のau基地局のバックホール回線にStarlinkを活用。第二段階として、特別なアンテナを必要としない「Direct to Cell」サービスを2025年4月に開始し、まずはSMSから、将来的には音声通話やデータ通信への対応も計画している。
- 株価への影響:自社の開発負担は軽く、より早期に収益化を実現できる可能性がある。パートナー依存リスクはあるものの、Starlinkとの提携進展や「圏外」解消によるコンシューマー向けサービスへの貢献が、株価を左右する。
拡大するエコシステム ― バリューチェーン全体の投資機会
NTN革命の影響は、通信キャリアに留まらず、広範な産業に波及する。NTNの実現を支える「縁の下の力持ち」企業群にこそ、分散された、しかし確実な投資機会が存在する。
コアインフラと通信機器(中期)
- 日本電気(NEC, 6701)と富士通(6702)は、HAPSに搭載される通信ペイロード、地上とHAPSを結ぶゲートウェイ局、NTN環境に対応した基地局ソフトウェアの開発・製造において中心的な役割を担う。 Beyond 5G/6Gを見据えた国家プロジェクトと連動しており、中期的な収益貢献が期待される。
専門技術と計測(短期)
- アンリツ(6754)は、NTN通信特有の課題(ドップラー効果、長大な伝搬遅延)を正確に再現し、通信チップセットや端末の性能を検証するための計測ソリューションを提供する。同社の製品はNTN対応機器の開発に必須のツールであり、NTN市場が拡大すればするほど、その需要は確実に増加する。アンリツは、どのキャリアの戦略が成功するかに関わらず、市場全体の成長から恩恵を受ける**「トールロード(料金所)」的なビジネスモデル**を持つため、短期間での業績インパクトが期待される。
- スカパーJSATホールディングス(9412)は、NTTとの合弁会社Space Compassを通じてHAPS事業の当事者となっており、長年の衛星運用ノウハウに加え、HAPSという新たな成長ドライバーを得る。短期的な収益インパクトが見込まれる。
アプリケーションとドローン産業(短期)
- ACSL(6232)は、国産ドローンのリーディングカンパニーであり、NTNによる信頼性の高い通信リンクの確立は、同社のビジネスモデルを根本から変える。NTNによって全国の山間部や離島でも安全なレベル4飛行が可能になれば、過疎地への物流や広大なインフラ点検といったユースケースが、実証から本格的な商業サービスへと移行する。キャリアグレードのNTN接続性は、ACSLのソリューションの信頼性を飛躍的に高め、官公庁や大手インフラ企業からの受注拡大に直結する直接的受益者となる。
先端素材と部品(長期)
HAPSの長期滞空を可能にするための高性能な素材と電子部品を供給する企業群は、長期的な構造的成長ポテンシャルを持つ。
- 先端素材: HAPS機体の極めて高い軽量性・高剛性・耐久性を満たすため、炭素繊維複合材料(CFRP)が不可欠となる。東レ(3402)と帝人(3401)は世界的なリーダーであり、HAPSの量産化が進めば安定した需要が見込まれる。
- パワー半導体: 太陽光を唯一の動力源とするHAPSのエネルギーマネジメントには、高効率な電力変換・制御を行うパワー半導体が不可欠である。特に電力損失が少ない炭化ケイ素(SiC)や窒化ガリウム(GaN)を用いた次世代材料が重要となる。ローム(6963)や富士電機(6504)は、この分野で高い技術力を持ち、高付加価値な製品を提供する機会を得る。
これらの「イネーブラー」企業への投資は、特定のキャリアの成功に賭けるリスクを分散させ、NTNというメガトレンド全体に分散投資する効果がある。
結論:投資テーマと戦略的提言
日本の空で始まろうとしている通信革命は、短期的なテーマ物色ではなく、次世代の産業革命を支える基盤そのものを構築する試みである。
投資家は、以下のドライバーとリスク要因を注視し、投資ホライズンに合わせたポートフォリオを構築することが重要となる。
注目すべきドライバー
- 技術的マイルストーン:HAPSの3ヶ月以上の連続飛行成功、NTN通信を用いたレベル4飛行の国内初成功など。
- 規制・政策の進展:国土交通省によるUTMサービスプロバイダ認定制度の正式な導入、およびNTNを前提とした運航ルールの策定。
- 大型契約の獲得:大手電力・ガス会社や防衛省、警察庁などからのNTNサービスやドローンソリューションの大型受注。
注意すべきリスク要因
- 技術的失敗:HAPSの試験機墜落や、開発コストが想定を大幅に上回る商用化計画の遅延。
- 規制の停滞:省庁間の制度調整の難航によるレベル4飛行の承認プロセスの停滞。
- 社会的受容性:ドローンやeVTOLの事故、騒音問題などによる社会的な逆風。
このNTNメガトレンドへの投資は、時間軸とリスク許容度に応じて、以下のように階層的にアプローチすることが有効である。
- Tier 1(直接的受益者): NTT、ソフトバンク、KDDI
- 市場創出から最も直接的な恩恵を受けるが、巨額の投資と戦略実行に関するリスクも最も大きい。
- Tier 2(中核的イネーブラー): スカパーJSAT、アンリツ
- 特定のキャリアの戦略に依存せず、NTN市場全体の成長から恩恵を受ける。特にアンリツは、開発初期段階での需要増加が見込まれる。
- Tier 3(長期エコシステム): ACSL、NEC、富士通、東レ、ローム、富士電機
- 市場が本格的に立ち上がるまでには時間を要するが、アプリケーション側での直接的受益者(ACSL)や、構造的な成長ポテンシャルを持つ素材・部品の供給者として、長期的な視点での投資機会を提供する。
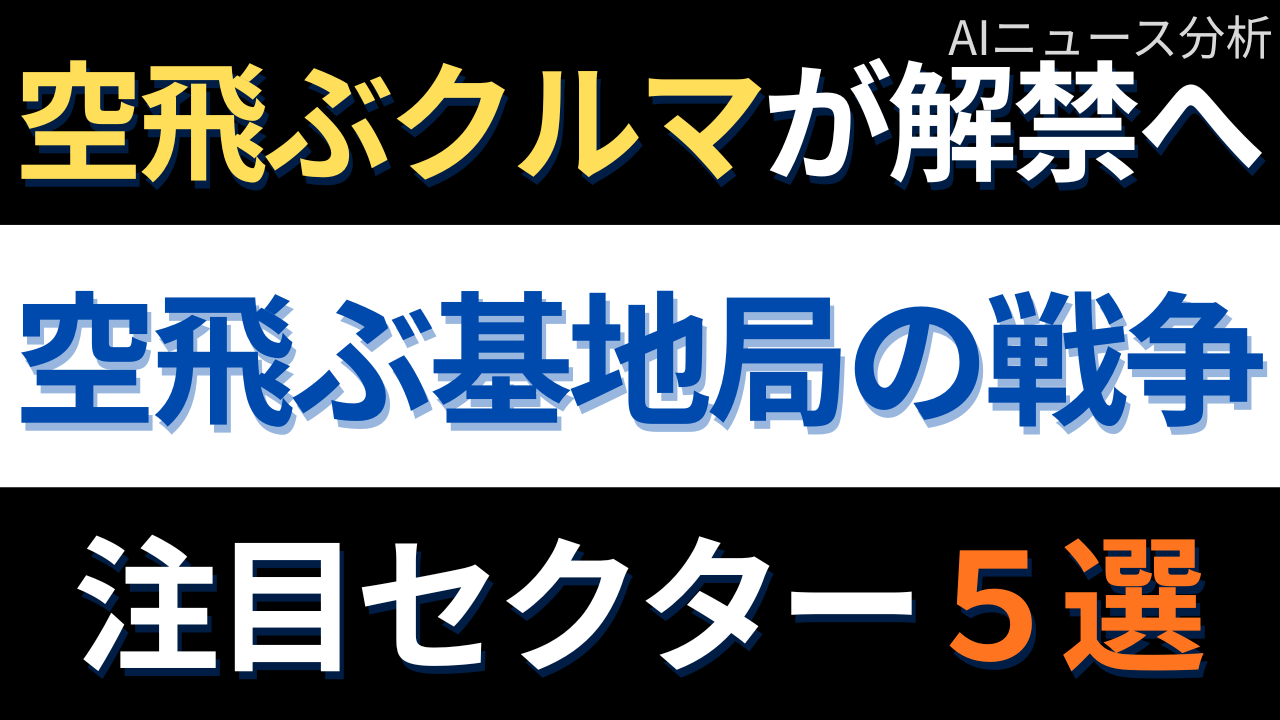


コメント