2025年10月9日の東京証券取引所取引終了後に発表されたスギホールディングス(7649)の2026年2月期第2四半期(中間期)決算は、売上高、各段階利益において前年同期比で大幅な増収増益を達成しました。特に親会社株主に帰属する中間純利益は前年同期比119.1%増と、驚異的な伸びを示しています。
しかしこの好調な決算にもかかわらず、発表後の時間外取引(PTS)では株価が下落するという逆説的な動きが見られました。終値3,380.0円に対し、PTSでは3,201.3円まで下落しています。
本稿では、決算内容の詳細を分析し、株価下落の背景にある市場の懸念、そして今後の見通しについて深く考察します。
第1章:2026年2月期第2四半期連結業績の概況
スギホールディングスが発表した2026年2月期中間期の連結業績は、国内経済の回復基調やインバウンド需要の増加を背景に、極めて力強い結果となりました。
驚異的な成長率を記録した主要利益指標
当中間期(2025年3月1日~2025年8月31日)の連結経営成績は以下の通りです。
- 売上高:5,001億72百万円(前年同期比20.9%増)
- 営業利益:236億96百万円(前年同期比16.8%増)
- 経常利益:242億36百万円(前年同期比12.9%増)
- 親会社株主に帰属する中間純利益:286億16百万円(前年同期比119.1%増)
売上高は5,000億円の大台を超え、前年同期比で2割増という高い成長率を達成。営業利益や経常利益の伸びも堅調ですが、注目すべきは純利益が前年同期の130億59百万円→286億16百万円へ倍以上(+119.1%)となった点です。一株当たり中間純利益も158.13円と、前年同期の72.17円から大幅に改善しています。
好調な業績を支えた要因
- 事業環境と物販・調剤領域の成長
雇用・所得環境の改善や訪日外国人旅行者数の増加により回復基調。物販ではインバウンド需要の獲得やH&BC、日用雑貨・食品が底堅く推移。調剤では高齢化を背景に処方せん応需枚数が伸長。調剤室・待合室の拡張・改装、高度処方への対応強化、連携医療機関の増加が売上基盤の拡充に寄与。 - DX化と店舗戦略の推進
アプリを活用した調剤DXによる生産性向上、購買データに基づく販促を推進。関東・中部・関西でのドミナント出店を進め、期末2,279店舗を展開。新規出店55店舗、調剤薬局70店舗の取得、改装138店舗で既存店競争力も強化。 - 会計処理上の特異点(税効果)
**純利益の+119.1%という高い伸びは経常利益の+12.9%**を大きく上回り、税金費用要因が大きいと考えられます。法人税等合計がマイナス62億85百万円、法人税等調整額がマイナス118億29百万円と大幅な益。繰延税金資産は192億4百万円→306億68百万円へ増加し、税務上の影響が純利益を押し上げた特異要因と推察されます。
第2章:PTS株価下落の「真の理由」考察
これほど好調な業績、特に純利益の三桁成長にもかかわらず株価が下落した最大の理由は、市場の期待値と通期業績予想との乖離にあります。
市場の期待値を満たさなかった「通期業績予想」
投資家が重視するのは実績だけでなく、企業が示す今後の見通し。同社は今回の2Q決算で、2025年7月10日公表の通期連結業績予想を据え置きました。
通期予想(2026年2月期)主要指標
| 指標 | 通期予想(百万円) | 対前期増減率(%) |
|---|---|---|
| 売上高 | 1,005,000 | 14.5 |
| 経常利益 | 50,500 | 20.3 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 44,200 | 72.1 |
進捗率の目安
- 純利益:286億16百万円(上期)/442億円(通期予想)=約64.7%
- 営業利益:236億96百万円(上期)/490億円(通期予想)=約48.4%
通常、上期で利益進捗が50%超なら上方修正期待が高まりやすいところ、据え置きは市場に**「下期は保守的(または税効果の一過性)」とのシグナル。結果、失望売りや将来成長スピードへの懸念からPTSで下落**した可能性が高いと言えます。
競争激化とコスト上昇の懸念
ドラッグストア業界は物価高による節約志向、薬価・調剤報酬改定、競争激化という逆風が継続。同社の販管費は前年同期比+25.2%(+266億7百万円)で、売上総利益の伸び(+23.9%)を上回る増勢。出店・DX・人員再配置は競争力を高める一方、コスト負担も増加。市場は下期のコスト上振れが利益を圧迫するリスクを警戒したとみられます。
第3章:将来の成長戦略と今後の見通し
短期的にはPTSで株価が下落しましたが、同社は業界再編を視野に重要な動きを見せています。
戦略的資本提携:株式会社セキ薬品の持分法適用会社化
重要な後発事象として、株式会社セキ薬品の持分法適用会社化が挙げられます。
- 契約・効力:2025年8月19日に株式譲渡契約締結、9月30日に効力発生
- 目的:両社の事業ノウハウ・リソース融合で事業成長を加速
- 取得詳細:持分比率49.0%(取得価額225億円)
さらに5年後を目途に追加取得の合意があり、実行されれば持株比率51.0%→連結子会社化見込み。これは関東エリアのドミナント強化と競争力向上に資する重要な一手です。
財務状況の健全性と投資活動
- 自己資本比率:49.8%(健全性を維持)
- 営業CF:+664億16百万円(前年同期比+21.9%)
- 主因:仕入債務+346億79百万円 など
- 投資CF:▲25億88百万円
- 収入:投資有価証券の売却・償還+104億64百万円
- 支出:有形固定資産取得▲101億93百万円
- セキ薬品株式取得(225億円)は借入で充当し、資金調達を活用
通期目標達成への期待と課題
通期売上高1兆円を目指し、2Q時点で約5割を達成。
一方の課題は営業利益の進捗が5割未満で、下期の効率化・コストコントロールが必須。
セキ薬品の将来連結化に向け、シナジー発現と利益率改善をどこまで前倒しできるかが、当期純利益442億円(+72.1%)達成の鍵です。
まとめ(投資家が注視すべき3点)
スギホールディングス(7649)の2026年2月期2Q決算は、売上+20.9%・純利益+119.1%の力強い内容。インバウンド、店舗戦略、調剤DXの成果が見えます。
一方で、通期予想据え置きが失望要因となり、PTSで株価は下落。市場は税効果による一過性や下期のコスト上振れを警戒しています。
注目ポイント
- 通期目標達成の確度:上期**純利益進捗約65%**が、営業面での実質成長で裏付けられるか。
- セキ薬品とのシナジー:関東エリア強化と将来の連結化に向け、売上・利益率へどこまで寄与するか。
- 利益率の改善:販管費増に見合う粗利改善と、DXによる生産性向上の実効性。
短期的には保守的なガイダンスが重しですが、業界再編を主導する提携戦略は中長期でポジティブ。投資家は一過性の純利益増ではなく、営業利益のトレンドと戦略M&Aの効果を冷静に見極める必要があります。


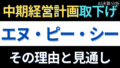
コメント