自民党と日本維新の会の連立政権合意書に記載された12項目(「12本の矢」)の内容解説と、それらの実現可能性について分析します。
この合意書は、日本が内外ともに厳しい状況にある中で、「日本再起」を図り、安定した政権を樹立するために、両党が国家観を共有し、全面的に協力することを決断したものです。この政策の実現には、憲法改正、安全保障改革、社会保障改革、統治機構改革を含む中長期の構造改革の推進が含まれています。
合意書全体を通じて、「〜を成立させる」「創設する」という強いコミットメントと、「検討する/制度設計を行う/目指す」という段階的な表現が混在しており、短期目標と長期プロセスを区別する二層構造となっています。
連立政権合意書に記載の12項目と実現可能性分析
1. 経済・財政関連施策
| 内容の解説 | 実現可能性の分析 | 根拠となる資料 |
|---|---|---|
| ガソリン税の暫定税率廃止:令和7年臨時国会中に法案を成立させる。 | 維新の看板政策であり、「最強文言」が使われている。政治優先度は高いが、財源の穴埋め(道路特定財源・地方交付)と与野党の攻防が最大の難関となる。減収補填策がセットでなければ与党内でも抵抗が出やすい。 | — |
| 物価対策の補正予算:電気・ガス料金補助を含め、臨時国会で成立させる。 | 与党中枢の最優先事項であり、成立見込みは高い。 | — |
| インフレ対応型税制:所得税の基礎控除等のインフレ連動化の制度設計を令和7年内を目途に取りまとめる。給付付き税額控除の導入も早急に制度設計を進める。 | 合意は強いが「制度設計止まり」の危険性がある。制度設計やシステム改修、所得捕捉に課題を抱える。骨子合意までは確度が高い。 | — |
2. 社会保障政策
| 内容の解説 | 実現可能性の分析 | 根拠となる資料 |
|---|---|---|
| 社会保障改革の推進:現役世代の保険料率の上昇を止め、引き下げることを目指す。応能負担の徹底(金融所得の反映、OTC薬自己負担見直し等)を実施する。 | 「令和7年度中に骨子合意→8年度制度設計→順次実行」という三段階の段階表現。保険者再編や窓口負担の公平化などは痛みを伴う「岩盤」で、政局化しやすい。 | — |
| 実現性:短期(骨子合意まで)は中〜高、中期(制度法案可決)は中、実装は低〜中。 | — | — |
3. 皇室・憲法改正・家族制度等
| 内容の解説 | 実現可能性の分析 | 根拠となる資料 |
|---|---|---|
| 皇室典範改正:男系継承を維持する前提で、「皇統に属する男系の男子を皇族とする養子縁組」案を第一優先とし、令和8年通常国会での改正を目指す。 | 争点性が高く、世論の熟議が必須であり、時間は要する。実現性は中。 | — |
| 改憲(9条/緊急事態条項):両党の条文起草協議会を臨時国会中に設置。緊急事態条項は令和8年度中の条文案国会提出を目指す。 | 協議会の設置自体は容易。ただし発議には衆参両院で2/3の賛成が必要で、国民投票の可決も要件。現状は要件不足とされ、フルパスでの実現は高難度。 | — |
| 旧姓の通称使用:社会生活で法的効力を持たせる制度を創設し、令和8年通常国会に法案提出。 | 与党内でも比較的合意を得やすい。実現性は中〜高。 | — |
4. 外交・安全保障
| 内容の解説 | 実現可能性の分析 | 根拠となる資料 |
|---|---|---|
| 抑止力強化:戦略三文書を前倒し改定し、スタンド・オフ防衛能力の整備(長射程ミサイル、陸上展開)を加速。次世代VLS搭載潜水艦の保有を推進。 | 既定路線の延長で前進可能。ただし、産業基盤・人材・サプライチェーンが制約。実現性は中〜高(段階実行)。 | — |
| 防衛装備移転:「防衛装備移転三原則の運用指針」の五類型を撤廃、GOCO方式(国営工廠・国有施設民間操業)を推進。 | 制度改定は可能だが、国内合意形成や透明性設計が課題。実現性は中。 | — |
| その他:外務省に和平調停部門を令和7年度中に創設。自衛官の恩給制度創設を検討し、「階級」「服制」等の国際標準化を令和8年度中に実行。 | 和平調停部門の創設は期日明記の短期KPI。自衛官の国際標準化は運用改訂で動かしやすい。 | — |
5. インテリジェンス政策
| 内容の解説 | 実現可能性の分析 | 根拠となる資料 |
|---|---|---|
| 国家情報局(R8通常国会)および対外情報庁(R9年度末まで)創設。情報要員養成機関の創設。スパイ防止関連法制の策定・成立を急ぐ。 | 政治意思は強い。成功の鍵は、省庁再編と個人情報保護・監督制度の精密設計。実現性は中(時間と合意形成に依存)。 | — |
6. エネルギー政策
| 内容の解説 | 実現可能性の分析 | 根拠となる資料 |
|---|---|---|
| 原発再稼働の推進、次世代炉・核融合炉の開発加速化。地熱など再エネの開発を推進。 | 地元同意や規制対応により速度は限定的だが、政策の方向性は容認が広がる。実現性は中。 | — |
7. 食料安全保障・国土政策
| 内容の解説 | 実現可能性の分析 | 根拠となる資料 |
|---|---|---|
| 施設型食料生産設備への大型投資を実現。大規模太陽光発電所(メガソーラー)の法的規制を令和8年通常国会で実行。 | メガソーラー規制は地方自治体の実務と連動。実現性は中。 | — |
8. 経済安全保障政策
| 内容の解説 | 実現可能性の分析 | 根拠となる資料 |
|---|---|---|
| 南西諸島における海底ケーブルの強靭性を強化する施策を推進。 | — | — |
9. 人口政策及び外国人政策
| 内容の解説 | 実現可能性の分析 | 根拠となる資料 |
|---|---|---|
| 人口減少対策本部を臨時国会中に設置。外国人政策の「量的マネジメント」を含む「人口戦略」を令和8年度中に策定。令和8年通常国会で「対日外国投資委員会(日本版CFIUS)」創設を目指し、外国人による土地取得規制を強化。 | 対策本部の設置自体は容易。量的マネジメントや土地規制強化は、経済界や国際関係との整合性が焦点。実現性は中。 | — |
10. 教育政策
| 内容の解説 | 実現可能性の分析 | 根拠となる資料 |
|---|---|---|
| 高校無償化/小学校給食無償化を令和8年4月から実施。制度設計を確定。大学数・規模の適正化を目指す。 | 政治的優先度が高く、合意も明確。財源と地方での実装が壁だが、実現性は中〜高(段階導入の可能性)。大学の適正化は調整が長期戦で実現性は低〜中。 | — |
11. 統治機構改革
| 内容の解説 | 実現可能性の分析 | 根拠となる資料 |
|---|---|---|
| 首都機能の分散(副首都構想)を目指す。令和7年臨時国会中に協議体を設置し、令和8年通常国会で法案成立を目指す。 | 維新の色彩が強い政策で連立の前提条件の一つ。所管横断課題と自治体合意が必要で長期化必至。実現性は中。 | — |
12. 政治改革
| 内容の解説 | 実現可能性の分析 | 根拠となる資料 |
|---|---|---|
| 企業・団体献金の取り扱い:両党で協議体を設置し、第三者委員会で検討を加え、高市総裁の任期中に結論。 | 自民は「公開」、維新は「完全廃止」と立場が明確に異なるため、現時点では結論先送り。検討色が強く、短期成立は難しい。実現性は低。 | — |
| 衆議院議員定数「1割削減」:臨時国会で議員立法案を提出し、成立を目指す。 | 巨大な選挙区再編を伴い、抵抗が強い。連立の前提条件とされたが、実現性は低〜中。 | — |
| 選挙制度の見直し:小選挙区比例並立制の廃止や中選挙区制の導入を含め検討。 | 制度合意の難易度は最上位。実現性は低。 | — |
総評:合意記載内容の実現可能性
合意文書に記載された政策の実現可能性は、その内容と目標期間によって、大きく三つの類型に分類されます。
1. 即時性の高い「やる」系(短期KPI)
- 特徴:「〜を成立させる」「創設する」のように強いコミットメントがあり、会期や年度が明記されている(短中期KPI)。
- 事例:物価対策の補正予算の成立、ガソリン暫定税率廃止法案の提出・成立(修正付きの可能性あり)、改憲に関する条文起草協議会の設置。
- 実現性:実現余地あり。ただし、財源・制度設計や与野党の力学により、骨抜き化や先送りリスクがある。
2. 制度大改革を伴う「工程合意」系(中長期プロセス)
- 特徴:「骨子を合意/制度設計を行い順次実行」「…を目指す」という段階的表現。合意したのは「やる工程」であり、「中身」はこれから決める構造。
- 事例:医療・社会保障制度改革、インフレ連動型税制(骨子合意まで)、国家情報局/対外情報庁の創設。
- 実現性:実装までは複数会期+政省令で長期戦。短期は骨子合意など入口まで進む確度が高いが、痛みを伴う岩盤改革は薄められたり段階化されやすい。
3. 政治的ハードルが極めて高い「本丸」系
- 特徴:衆参両院での3分の2の賛成や国民投票、または両党間の根深い立場差の克服を要する案件。
- 事例:憲法改正(発議→可決のフルパス)、国政選挙制度の抜本見直し(中選挙区制導入など)、企業・団体献金の完全廃止。
- 実現性:最もハードルが高い。企業・団体献金のように、合意書の中で結論の先送りが明確に示されているものもある。
自民党は「工程」を積み上げる能力に長けているため、時間をかければ既定路線化する体力がある一方、今回は維新の“政策取引”により短期パッケージが前面に出ています。しかし、議席は単独過半数に満たないため、重要法案では野党協力が都度必要となり、最終形は「調整型」に寄る可能性が高いと分析されます。
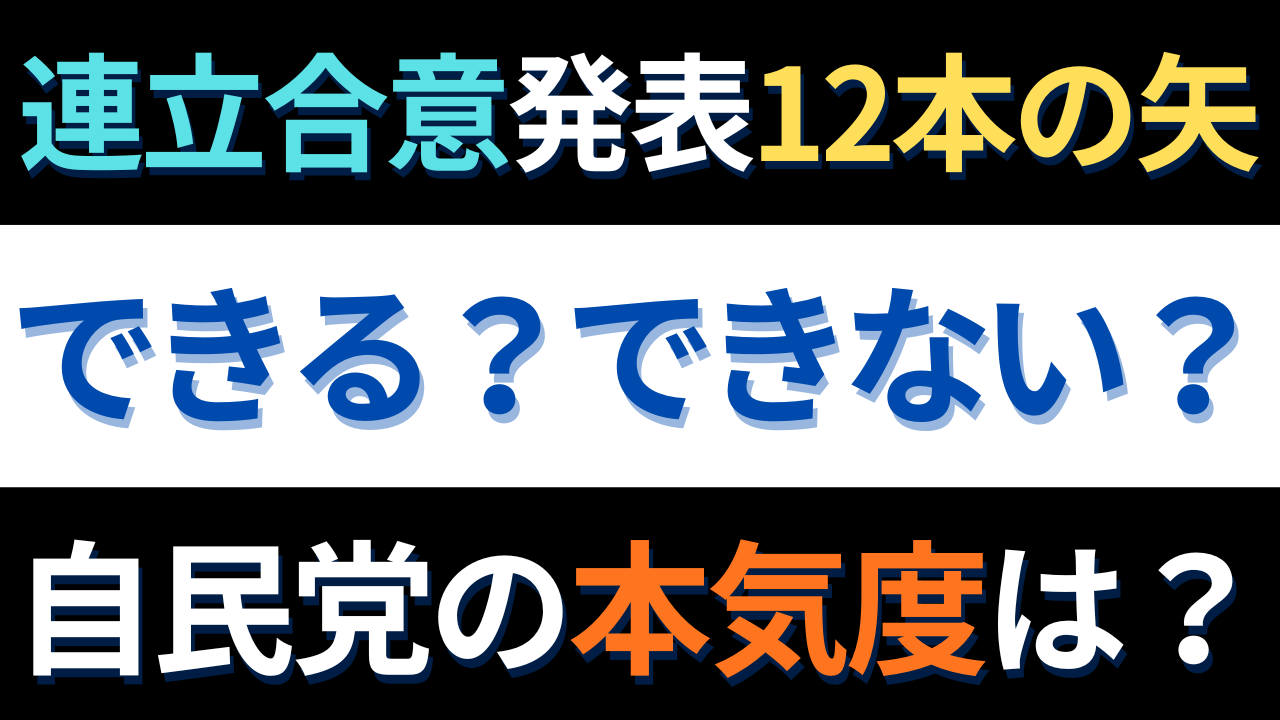
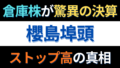
-15-120x68.png)
コメント